昨日(8月28日)の讀賣新聞が自社の記者が、週刊誌に情報を漏らしたとの記事を掲載した。さらに今朝の朝日新聞、東京新聞までもそれを受ける形で記事を掲載している。「おー大変な時代だなぁ、昭和で良かった❓」と言うのが最初の感想だった。

すぐ思ったのは、讀賣といえば政治家やその関係者に情報で取り入り、派閥の領袖に食い込み、社内でのし上がり、今でも確かトップの主筆として君臨するW邊恒雄氏の場合はどう判断するのだろう。情報は誰のものなのかを突き詰めれば、そこに行きあたる。
相手が週刊誌記者や民放の記者で、しかも女性だからダメで、相手が政治家やその周辺ならいいのか❓外部からクレームが来たからか。
時代が違うと言ってしまえば、そうなのかと思わざるを得ないのだろうが、私が知っているかつての朝日新聞のトップも記者も、東京新聞の編集委員や記者も、産経の記者も、週刊誌との付き合いを書き出したら「列伝」が一冊出来てしまう。
NHKでも、今も語り草になっている大記者(故人)の女性週刊誌との太いパイプは誰もが、随分後輩の私ですら知っているくらいだ。彼は警視庁や司法クラブでキャッチした芸能ネタまでも、仲のいい週刊誌に特ダネとして提供していて、そのために後輩記者に張り番までさせていたという。これは張り番をした本人から直接聞いたから本当だろう。普段から特ダネを取ることで定評があった伝説の記者で、退職後も司法クラブにふらりと来るとI 手上伸一キャップが緊張していたぐらいだから、やはり凄い記者だったのだろう。
名前を書けば誰でも知っている超著名な元社会部記者( I 上彰さんではない)もすごかった。女性週刊誌が社会部に直接届くと、それを手にして彼はニコニコしながら、「週刊誌と付き合えないような記者なんて(その程度だ)」と堂々と言っていた。彼の誠実さや多岐に渡る取材先との深い関係には、周りは一目も二目も置いていた。今も私が尊敬する先輩記者の一人だ。
浩宮の結婚が決まる直前、すでにNHKを辞めていたけれど、電話でまるで社会部長やデスクのように指示、差配してくれて上手く行った、という以上に完勝だった。小和田雅子さんをずっとマークしていたから氏の紹介で、大親友の2人の女性がスタジオに来てくれて、しかもアルバムやビデオまで持参してくれて、思い出を語りあったのは誰の記憶にあるだろう。ひと段落したところでT原幹治社会部長がお礼を言っていた。
私が敬愛する政治部長、報道局長、理事だった故 滋野武さんは、「週刊誌には貸しは作っておけ、いつか世話になることもある」と何度も聞かされた。まだ新聞、テレビの方が情報を持っていた時代の話だ。平成の後半から令和の時代は、新聞、テレビの方が「文春砲」など週刊誌情報に右往左往させられるようになった。まだ取材では未熟かもしれないが、いずれSNSが特ダネを連発する日もそう遠くないだろう。
もちろん当時でも口うるさく、「週刊誌でバイトする奴がいる」「情報を流している奴がいる」と罵る先輩もいた。別に金を貰うわけではないからバイトではないのだが、情報の取れない記者の嫉妬だと思っていた。そんな記者に限って教訓話が大好きだった。そのな話をする暇があったら夜回りにでも行ってこいよと思っていた。いつの間にか社会部どころか報道の世界から消えてしまった。こんなこと詳細に書き出したら、今もまだ役員やトップに君臨する各社の記者出身の幹部たちは、何と言うだろう。

この短い原稿だと讀賣新聞記者の扱った記事は非常に興味深い内容で、大いに関心があるし記事にして然るべきもののように思える。さらに動機が、女性記者の歓心を買うことにあったようだが、逆に見れば週刊誌や民放の女性記者は立派なもんだ。「自分以外は全て情報源」というのが私のスタンスで、家族だろうが恋人だろうが、ネタを持っている人はみな情報源なのだ。どうな方法でアクセスしようが情報は情報である。
讀賣といえば『不当逮捕』の立松和博さんは、相当なドンファンだったと本田靖春さんが事あるごとに話していた。当時は女性記者は皆無だろうし、女性週刊誌も草創期だから付き合いはなかっただろうが、今回の記者のことは、案外「なかなか大したもんだ」ぐらい言って立松さんも本田さんも大いに笑っていたのではないかと思う。そうめくじら立てんとという大らかさ、野武士的な雰囲気が昔の讀賣にはあった気がする。なかなか難しい性格の特捜部長に食い込む優れた司法記者で、温厚かつ、それこそ大らかだったY口寿一さんなら、こんなことわざわざくだくだ書かなくていいのにと思うのでは。
ひょっとしたら、いつか彼が讀賣のスキャンダルを救ってくれることがあるかもしれないではないか。「貸しは作っておけ」滋野さんの言葉は箴言であった。
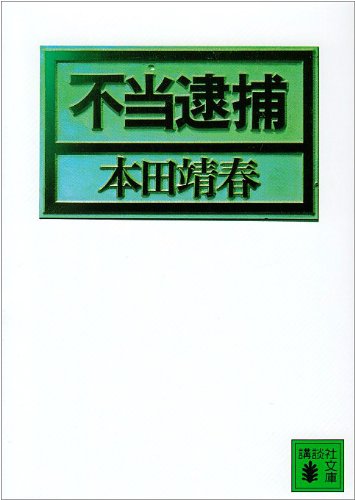
情報は誰のものか❓基軸はここにある。自分の社で使わないのなら、埋もれさせてはならない情報は、何らかの方法、何らかの形で発表しないと誰も知らないまま、限られたメディアによって握りつぶされてしまう。さらに権力に密かに渡されて恫喝の道具に使われてしまうこともありうる。
思えば最もコンプライアンスとほど遠い記者が、コンプライアス担当役員になった時、昔の仲間が集まると、みんなで飲みながら大いに笑って祝福したものだ。昭和は、記者には大らかな好い時代だった。四角四面の今の記者の世界が気の毒でならない。

